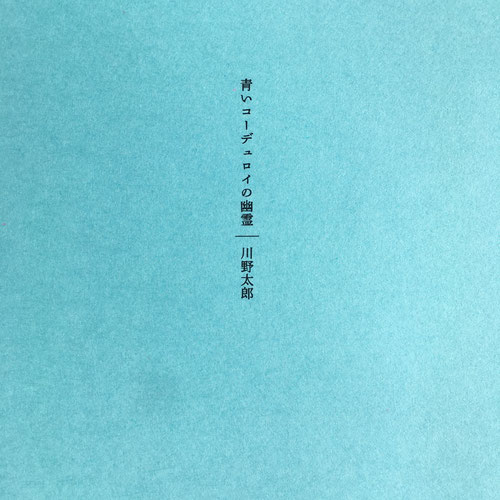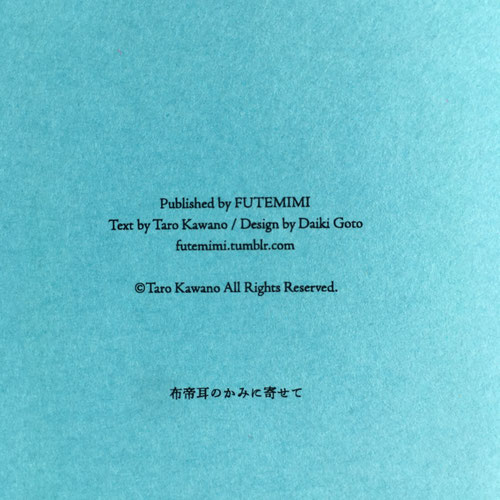川野太郎
2020/11/17
二十世紀半ばのカナダを舞台にした小説『ノーザン・ライツ』は、ひとりの少年をみまう水難事故の報せからはじまる。語り手ノア・クライニックの友人ペリー・ベイは、池の上で一輪車の曲芸をしているとき、割れた氷の下に落ち、亡くなる。
彼が暮らしたマニトバ州北部の村に「遺品」が残される。ペリーのおじであり、里親のサミュエルは、沈んでいた一輪車が錆び付いた姿でふたたび岸に打ち上げられているのを発見する。ノアは、ベッドの下にある、ペリーが描いた村の人々のスケッチを眺める……。
残された物を通じて、いまはもう目の前にいない人を思い出すという不思議に、あらためて打たれる。それは、その品々と縁のあった人がもういない、ということを強く感じながら、一方でその人がいるという感触を確かに感じてもいるという、どこか矛盾を含んだ経験だ。
あいだに本当になにも(物も、言葉も、風景も)介さないまま、ふとだれかのことが脳裏をよぎる、ということがありうるのかどうか、わからない。だがいずれにしても、「その人がもういない」状況と「その人の存在を感じる」感覚がぴったり重なっている瞬間は、残された物がそこにあるからこそ、いっそう際立つように思われる。
それが人の身体を包む衣服のようなものであれば、なおさら。
ペリーの喪に服す村の人々がダンスパーティーを催したとき、とりわけ忘れがたいことが起こる。ペリーのおばのヘティーがひとりの友人をふと見ると、彼が、ペリーが生前によく着ていた青いコーデュロイの上着を着ているのだ! へティーは驚き、彼をはげしく糾弾する。「どうしてあなたが着ているの?」しかし奇妙なことに、そのとき居合わせたほかの人々が見た彼が着ていたのは、ワイシャツだった。
後日、村の会合が開かれる。話題はもちろん、あの日へティー以外には見えなかったペリーの上着だ。参加者のひとりが言う、「彼女にとっての幽霊、ということだな。残りのおれたちにとってはそうじゃなかった、そういうことかい?」
たくさんの意見が交わされる。「幽霊」はヘティーひとりの悲しみが見せた幻影にすぎないのだろうか? そうだとするなら、彼女が見たのがペリーその人の幽霊ではなく彼が着ていた上着の幽霊だったのは、どういうことなのだろう?
ここで話し合われているのはきっと、たんなる「心霊現象」のあるなしではない。遠くにいる人のことを、しかしありありと感じること。そしてそういうときにはきまって、わたしたちの心の外側にあって、見たり、触れたり、聞いたりすることのできる「物」の影があること――その根源的な不思議に、彼らは心を奪われてしまったように見える。
取り残されたと感じるとき、立ち去った人の残した物たちを手がかりに、世界の基本の働きを眺めなおそうとすることが、わたしたちにはあると思う。
*ハワード・ノーマン『ノーザン・ライツ』川野太郎訳、みすず書房、二〇二〇年。
*2020年11月17日、八女「FUTEMIMI」でのイベントにあわせて小冊子の形で発行したエッセイ。
*発行:FUTEMIMI/デザイン:後藤大樹/製本:山本千聖 with FUTEMIMI and their friends
©️Taro Kawano